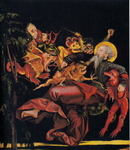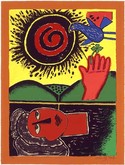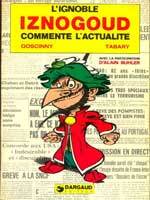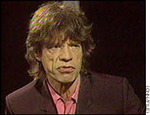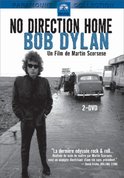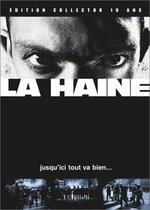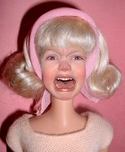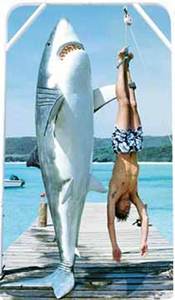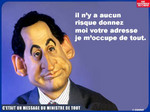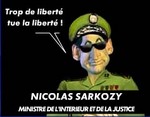"Rien ne sépare les enfants d'immigrés du reste de la société"
LE MONDE 12.11.05
En 1995, vous analysiez la "fracture sociale", expression dont le candidat Jacques Chirac s'était alors servi avec succès pour sa campagne présidentielle. Dix ans après, où en est-on ?
L'expression "fracture sociale" n'est pas de moi. Elle est de Marcel Gauchet, mais elle m'est invariablement attribuée. Tant pis, j'ai renoncé à lutter. Dans une note de la Fondation Saint-Simon, à l'époque, j'avais décrit la réapparition des forces populaires après l'effondrement du communisme, en rappelant que les ouvriers et les employés représentaient toujours 50 % de la population. Au simple vu des recensements, l'idée giscardienne des "deux Français sur trois" dans les classes moyennes ne tenait pas.
Entre deux élections, la classe politique se laisse régulièrement aveugler par les sondages d'opinion, qui sont le reflet des couches supérieures de la société. Cela donne ces enquêtes qui montrent que Balladur va être élu, que les référendums vont passer facilement... Ce n'est que pendant les campagnes électorales que les milieux populaires s'activent progressivement. Chacun croit alors assister à un changement d'humeur de l'électorat, quand il s'agit, en fait, de l'émergence de l'opinion populaire : celle des gens qui n'ont pas forcément un avis sur tout à tout moment.
Depuis dix ans, scrutin après scrutin, l'aliénation des milieux ouvriers et populaires à l'égard de la classe dirigeante au sens large n'a fait que croître : les résultats du dernier référendum du 29 mai sur l'Europe l'ont bien montré.
Les violences dans les banlieues françaises sont-elles une conséquence de cette aliénation ?
Dans les années récentes, la vie politique française n'a été qu'une suite de catastrophes qui laissent les observateurs étrangers de plus en plus stupéfaits et narquois. La première catastrophe, c'est la présidentielle de 2002, avec un premier tour qui amène l'extrême droite dans le duo de tête et un second tour où Jacques Chirac est élu avec plus de 80 % des voix.
La deuxième catastrophe, si l'on se place du point de vue des classes dirigeantes, c'est le référendum sur l'Europe. Pendant des mois, tous les commentateurs étaient convaincus que le oui allait passer et, à la fin, le non l'a emporté haut la main. Choc, surprise, abattement. Les classes dirigeantes commencent tout juste à se rendormir, en tentant de se persuader que la société est redevenue stable, quand survient la troisième catastrophe : cet embrasement des banlieues dont nul ne sait encore s'il est terminé. Et, chaque fois, la délégitimation des classes dirigeantes devient plus flagrante.
Le scénario des catastrophes dont vous parlez est-il toujours le même ?
Non, elles ne font pas agir les mêmes couches. Le Pen au second tour en 2002, c'est le vieux monde populaire français qui forme le coeur du vote FN. Le non au référendum, c'est l'entrée en scène d'une partie des classes moyennes, liée à la fonction publique, que je qualifierais de petite bourgeoisie d'Etat. La troisième catastrophe, celle des banlieues, met en jeu d'autres acteurs : des jeunes issus de l'immigration. Ceux-ci sont encore séparés des milieux populaires français pour des raisons historiques et culturelles, bien qu'ils appartiennent au même monde en termes sociaux et économiques. Les trois groupes que je viens de décrire ont en commun un antagonisme à l'égard du système et des classes dirigeantes.
En revanche, on ne voit pas apparaître de solidarité entre eux. Par exemple, je reste persuadé que les deux classes qui ont produit le non au référendum les milieux populaires et la petite bourgeoisie d'Etat ont des intérêts profondément divergents. Les premiers sont en rage contre le statu quo, qui signifie, pour eux, chômage et écrasement des salaires dans un monde ouvert à la concurrence ; la seconde désire le maintien du statu quo, qui la laisse à l'abri du libre-échange et lui assure une garantie de l'emploi.
N'y a-t-il pas un antagonisme entre ces deux catégories et la troisième, celle des jeunes issus de l'immigration qui brûlent des voitures ?
C'est très inquiétant de voir brûler des voitures, des autobus et des maternelles. Et les choses peuvent encore dégénérer. Malgré tout, je penche pour une interprétation assez optimiste de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de la situation des banlieues, qui est par endroits désastreuse, avec des taux de chômage de 35 % chez les chefs de famille et des discriminations ethniques à l'embauche.
Mais je ne vois rien dans les événements eux-mêmes qui sépare radicalement les enfants d'immigrés du reste de la société française. J'y vois exactement le contraire. J'interprète les événements comme un refus de marginalisation. Tout ça n'aurait pas pu se produire si ces enfants d'immigrés n'avaient pas intériorisé quelques-unes des valeurs fondamentales de la société française, dont, par exemple, le couple liberté-égalité. Du côté des autres acteurs, la police menée par le gouvernement, les autorités locales, la population non immigrée, j'ai vu de l'exaspération peut-être, mais pas de rejet en bloc.
Voulez-vous dire que les jeunes se révoltent parce qu'ils ont intégré le modèle républicain et sentent qu'il ne fonctionne pas ?
Exactement. Je lis leur révolte comme une aspiration à l'égalité. La société française est travaillée par la montée des valeurs inégalitaires, qui touche l'ensemble du monde développé. Assez bien admise aux Etats-Unis, où son seul effet politique est le succès du néoconservatisme, cette poussée inégalitaire planétaire passe mal en France. Elle se heurte à une valeur anthropologique égalitaire qui était au coeur des structures familiales paysannes du Bassin parisien. Ce substrat, qui remonte au XVIIe siècle, ou plus loin encore, ne se retrouve pas du tout dans la paysannerie anglaise, chez qui la transmission des terres était inégalitaire.
Quand on est en haut de la société, on peut se faire à la montée de l'inégalité, même si on est contre sur le plan des principes : ce n'est pas trop inconfortable. En revanche, les milieux populaires ou les classes moyennes la vivent très mal. Cela donne le vote FN, qui a une composante d'égalité, avec cette capacité à dire merde aux élites, et une composante d'inégalité, avec le fait d'aller chercher plus bas que soi l'immigré bouc émissaire.
Pour ce qui est des gosses de banlieue d'origine africaine ou maghrébine, ils ne sont pas du tout dans la même situation que les Pakistanais d'Angleterre ou les Turcs d'Allemagne. Chez nous, les taux de mariages mixtes tournaient au début des années 1990 autour de 25 % pour les filles d'Algériens, alors qu'ils étaient de 1 % pour les filles de Turcs et d'epsilon pour celles de Pakistanais. La simple mixité ethnique des bandes de jeunes en France est impossible à concevoir dans les pays anglo-saxons. Evidemment, je ne suis pas en train de donner une vision idyllique de la France de 1789 qui serait à l'oeuvre, avec le postulat de l'homme universel, ce rêve des nationaux républicains.
Que pensez-vous de la réaction de la République face aux émeutes ?
Je n'étais pas contre la possibilité d'un couvre-feu devant des violences vraiment inquiétantes. Dans l'ensemble, je trouve que la réaction de la police et du gouvernement a été très modérée. En mai 1968, on criait bêtement "CRS : SS", mais, en face, les forces de l'ordre ont fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle. A l'époque, les milieux de gauche disaient que la police n'avait pas tiré parce que la bourgeoisie ne voulait pas tuer ses propres enfants.
Là, dans les banlieues, on a vu que la République ne tirait pas non plus sur les enfants d'immigrés. Ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas seuls concernés. Il y a eu un effet de capillarité entre toutes les jeunesses, même au fin fond de la province française. Le premier décès, périphérique aux événements, a entraîné une décrue immédiate. La presse étrangère qui ricane de la France devrait méditer cet exemple.
Je trouve d'une insigne stupidité de la part de Nicolas Sarkozy d'insister sur le caractère étranger des jeunes impliqués dans les violences. Je suis convaincu au contraire que le phénomène est typique de la société française. Les jeunes ethniquement mélangés de Seine-Saint-Denis s'inscrivent dans une tradition de soulèvement social qui jalonne l'histoire de France.
Leur violence traduit aussi la désintégration de la famille maghrébine et africaine au contact des valeurs d'égalité françaises. Notamment l'égalité des femmes. Pourtant, malgré les soubresauts inévitables, la deuxième et la troisième génération de fils d'immigrés s'intègrent relativement bien au sein des milieux populaires français, et certains rejoignent les classes moyennes ou supérieures.
Si je ne suis pas optimiste sur le plan économique je pense que la globalisation va peser de plus en plus sur l'emploi et les salaires , je suis optimiste sur le plan des valeurs politiques. En termes de résultat, après ces deux semaines d'émeutes, que voit-on ? Ces gens marginalisés, présentés comme extérieurs à la société, ont réussi à travers un mouvement qui a pris une ampleur nationale à intervenir dans le débat politique central, à obtenir des modifications de la politique d'un gouvernement de droite (en l'obligeant à rétablir les subventions aux associations des quartiers). Et tout ça en réaction à une provocation verbale du ministre de l'intérieur dont on va sans doute s'apercevoir qu'ils auront brisé la carrière. On peut être plus marginal !
***
Emmanuel Todd, 54 ans, est historien et démographe. Essayiste original, il a notamment publié, en 1994, Le Destin des immigrés (Seuil).
Propos recueillis par Raphaëlle Bacqué, Jean-Michel Dumay et Sophie Gherardi
Article paru dans l'édition du 13.11.05
 RESO/レゾ という名の左派グループサイトのアンチ・サルコキャンペーン。
RESO/レゾ という名の左派グループサイトのアンチ・サルコキャンペーン。