ね式(世界の読み方)
Il faut cultiver son jardin
« 2005年12 月 | メイン | 2006年2 月 »
2006-01-28
画像日記、Hamas etc.
投稿情報: 2006-01-28 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
2006-01-26
改題: BHL もなー、など
 “Everything, my dear. I will tell you. Sometimes in your private life you have a mistress you love, love being with. You spend time to time in a grand hotel, with good room service, great champagne, and you separate—and when you are really in love with her, you inevitably think, Could I wake up with her, near her every morning ? And then you try it. This is exactly what I did in America. America was a great mistress. I had a great fuck with America. It was like a weekend in the Hotel du Cap.”
“Everything, my dear. I will tell you. Sometimes in your private life you have a mistress you love, love being with. You spend time to time in a grand hotel, with good room service, great champagne, and you separate—and when you are really in love with her, you inevitably think, Could I wake up with her, near her every morning ? And then you try it. This is exactly what I did in America. America was a great mistress. I had a great fuck with America. It was like a weekend in the Hotel du Cap.”
さて、今日は引用から初めてみました。で、クイズ。
“what did he like best about the U.S.?” という質問に上のような答えを出したファキン・アウトな人物は誰でしょうか?
回答は明日のブログで、、とすると続かないのですぐネタあかし:
これはNew York Magazine に掲載された BHL/ ベルナール・アンリ・レヴィの書評・インタヴュー最後部分です。
前後関係を解説しますと、われらがヌーベル・フィヒロゾフ生き残り軍団の一人BHL(57歳)は2004年、トックヴィルの跡をたどって合衆国を(運転手に運転させて)回ったわけだ。それで書かれた文章は月間紙The Atlantic にまず掲載され、今回“ American Vertigo ” として出版されたのですね。
なお、この本をめぐって、BHLとネオコン頭脳クリストルとのあいだに論争があったようである。ル・モンドの記事から、
France - Etats-Unis, le match Lévy-Kristol /フランスvsアメリカ合衆国、レヴィ-クリストル
NY駐在記者Corine Lesnes の記事タイトルを真に受けてはいけません。これはジョークだね。世界民主化=商業化、という大きな野望が結局世界ドツボ化に繋がった。このきわめて近所迷惑なアヴァンチュールの脳内製造元ネオコン論客を合衆国代表とみなすのも、同様にタレントさんにして女優さんの夫兼業のBHLをフランス代表と受け取るのも、短絡した昨今のメディア商法パロディでしょう。記事によると、ウォール・ストリート・ジャーナルはBHLを“anti-anti-américain”、New York Magazineは“rock star French philosophe”と形容。ふーん。ポスト・ジジェクをねらったアンチ・アメリカンマーケティングね。
残念ながら、該当BHL新刊を読む機会はないと確信ありなので、アメリカン・ヴァーティゴオへの言及はいたしません。そういやあ、テレビでは何回も見たけど、BHLの文章読んだことないわ。なお関係ないですが、他の欧州諸国に比べ仏国パスポート保持者の合衆国ビザ申請拒否率がかなり高いらしい。。。関連記事 500 000 Français privés d'Amérique
***
 こっちは冗談ではない、大変事であります。パレスチナ自治評議会選でハマスが勝利。
こっちは冗談ではない、大変事であります。パレスチナ自治評議会選でハマスが勝利。
関連ル・モンド記事、Le Hamas obtient la majorité absolue au Parlement palestinien
シャロンの軍人および政治家としての評価はさておき、怖いのは対するイスラエル権力空洞です。同時に、ネオコンの妄想した“力(+金)による民主主義確立”、東欧では今までのところ成功しているように見えますが、中東では逆にベクトルが動く。イラン・イラクもそうですが、世界地政無視界飛行の観がある。由々しい事態です。
****
さて、左上の写真はこないだネットで見つけたドアノー/Robert Doisneau の写真。いつものように本文とはまったく関係ありません。アプレ・ゲール@サンジェルマン、キャーヴ/地下のジャズクラブ風景と思われますが、夢見るように踊る彼女の表情と、それに魅入られる彼の視線がバンリュウの魔術師ドアノーによって永遠化されています。んー、写真って凄いですねえ。
*****
もひとつ追加: まえにも紹介したreso/レゾのアンチ・サルコサイトでこんなの見つけました。Kit de formationをクリックすると、
Que faire face à la police ?
Guide pratique du manifestant arrêté, rédigé par le syndicat de la Magistrature /ポリスを目の前にして、どうする?デモで捕まった時どうするかという法律専門家のアドヴァイス、とか
Voyage dans la gauche / 左翼の旅、をクリックすると左翼の歴史や有名人紹介ページなどにぶち当たります。まだ全部に眼を通してないけど、書き方は極めて正統派(?!)。フランスでの長いサの歴史がこうゆーのを可能にしてるんだろうね。A SUIVRE...
参考:それぞれのぺージURLをクリップできないのが残念。またフランス語読みでは(まだ)ないレクターは、これとか使って英語化するといいと思う。 また、この仏語ぺージではいろんな翻訳ツールが見つかります。
投稿情報: 2006-01-26 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
2006-01-25
ウサマとマーケティング
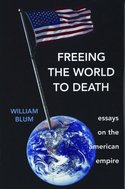 この頃、(不思議な現象だが)こちらではあんまり話題に登らない米国なんですが、これは面白い。ベン・ラデンが久々にメディアに登場、『アメリカ人、この本読むべし。』と、2000年に出版された “Freeing The World To Death アメリカ帝国に関するエッセイ” という本を(結果的に)プロモートしたわけ。おかげで米アマゾンで205763番目にランクされてたこの本、いっぺんにチャート26番目になっちゃった。
この頃、(不思議な現象だが)こちらではあんまり話題に登らない米国なんですが、これは面白い。ベン・ラデンが久々にメディアに登場、『アメリカ人、この本読むべし。』と、2000年に出版された “Freeing The World To Death アメリカ帝国に関するエッセイ” という本を(結果的に)プロモートしたわけ。おかげで米アマゾンで205763番目にランクされてたこの本、いっぺんにチャート26番目になっちゃった。
恐るべき影響力なんですが。ま、青年ベン・ラデンを対ソ戦でクリックし続けてあそこまで育てたのは米国CIAだったりしますから、論理的整合性がないといえない事もございませんね(恐怖の二重否定使ってみました)。恐るべきマーケティング自家免疫性抗原病なり。また、かのウォルフォ氏は世界銀行内部清掃でお忙しいようですし、結局宇宙空間はワープしてて、自分の投げたブーメラン石が(翌日訂正:ブーメランは直線空間でも戻ってくるがね、)自分のアタマ後部にぶち当たる可能性大なのでしょうか。コイズミさんもキヲツケよー。
関連ワシントン・ポスト記事。
投稿情報: 2006-01-25 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
2006-01-24
“パリのアメリカ人” -- ウィリアム・クライン展
 年末のすき焼きオフのながれで、なにやらアートなこの頃。今日はshibaさんと一緒にポンピドゥーセンターのWilliam Klein展に行ってきました。ひとりだとボーっとしてるうちに最終日は過ぎていた、、という情けない場合が多いし、特に日が短い冬は出るのが余計おっくう。その点誰かと誘い合わせてっのは、無精者には良き“テク”であります。
年末のすき焼きオフのながれで、なにやらアートなこの頃。今日はshibaさんと一緒にポンピドゥーセンターのWilliam Klein展に行ってきました。ひとりだとボーっとしてるうちに最終日は過ぎていた、、という情けない場合が多いし、特に日が短い冬は出るのが余計おっくう。その点誰かと誘い合わせてっのは、無精者には良き“テク”であります。
 さて、写真展はこれまであまり興味がなかったんですが、クラインは日本での友人に(米国に行ったまま音信不通の)カメラ男がおって、写真集を見せられた記憶がある。あと、ついついタブロー(絵画)の方に焦点が行きがちなんだが、パリでは写真展も多いんでこれも門前の小僧、自然に眼は肥えますね。クラインは写真ばかりではなく、絵・映像にも手を出すマルチタイプな人。その作品の全体像が掴めそう、、ということで行ってみる気になりました。
さて、写真展はこれまであまり興味がなかったんですが、クラインは日本での友人に(米国に行ったまま音信不通の)カメラ男がおって、写真集を見せられた記憶がある。あと、ついついタブロー(絵画)の方に焦点が行きがちなんだが、パリでは写真展も多いんでこれも門前の小僧、自然に眼は肥えますね。クラインは写真ばかりではなく、絵・映像にも手を出すマルチタイプな人。その作品の全体像が掴めそう、、ということで行ってみる気になりました。
今回のエクスポの詳しい内容はshibaさんが書いてるんで、ここでは私の印象を勝手に並べてみましょうか。。。
 ドアノーやカルティエ・ブレッソンの撮る写真、もちろんすばらしいですが、クラインのとはどこか違います。ドアノーもカルティエ・ブレッソンも、言ってみれば“絵画”的。アングルや瞬間が、直感によるものか計算によるものなのかは分かりませんが極めて洗練されています。これは同時に、スタティック/静止してるとも言えるわけだ。オブジェと写真家の間には距離がある。その点、クラインはもう一歩オブジェたる人間に近づく。群衆の中に入り込み、同じ高さで写真を撮ってると感じる。異形の者としての人間を撮り続けるんだが、、そしてこの異形の者達にはファッション・モデルや有名人も入るね、、、自分(クライン)自身もその異形の者のひとりであるんだと彼は考えてるんですね、きっと。ここから来るんだろう、被写体と写真家の間に一種の“correspondance/ 照応”を作り出している。共犯関係に近いかもしれない。フェリーニにも近い。(実際、クラインはローマでフェリーニの仕事を手伝うはずだったけれども実現しなかったようです。)そして、ドアノーやカンティエ・ブレッソンにはない“動き”がある。ダイナミズムと言えるか。それはクラインの撮る社会自体の持つダイナミズムでもあるな。
ドアノーやカルティエ・ブレッソンの撮る写真、もちろんすばらしいですが、クラインのとはどこか違います。ドアノーもカルティエ・ブレッソンも、言ってみれば“絵画”的。アングルや瞬間が、直感によるものか計算によるものなのかは分かりませんが極めて洗練されています。これは同時に、スタティック/静止してるとも言えるわけだ。オブジェと写真家の間には距離がある。その点、クラインはもう一歩オブジェたる人間に近づく。群衆の中に入り込み、同じ高さで写真を撮ってると感じる。異形の者としての人間を撮り続けるんだが、、そしてこの異形の者達にはファッション・モデルや有名人も入るね、、、自分(クライン)自身もその異形の者のひとりであるんだと彼は考えてるんですね、きっと。ここから来るんだろう、被写体と写真家の間に一種の“correspondance/ 照応”を作り出している。共犯関係に近いかもしれない。フェリーニにも近い。(実際、クラインはローマでフェリーニの仕事を手伝うはずだったけれども実現しなかったようです。)そして、ドアノーやカンティエ・ブレッソンにはない“動き”がある。ダイナミズムと言えるか。それはクラインの撮る社会自体の持つダイナミズムでもあるな。
 “Anything goes”、これはクラインの言葉ですが、まさにクラインは自由に時代を撮り続けます。ベトナム戦争に反対するニューヨーク学生デモの写真が不思議なほど “今”なのでびっくりする。同時に過去の作品をペイントした“コンタクツ・ペイント”は最近製作されたものですが、クラインは77歳の今でも(そして愛妻 Jeanneの亡くなった今も)変わっていないんですね。
“Anything goes”、これはクラインの言葉ですが、まさにクラインは自由に時代を撮り続けます。ベトナム戦争に反対するニューヨーク学生デモの写真が不思議なほど “今”なのでびっくりする。同時に過去の作品をペイントした“コンタクツ・ペイント”は最近製作されたものですが、クラインは77歳の今でも(そして愛妻 Jeanneの亡くなった今も)変わっていないんですね。
60年前後にニューヨーク、東京、モスクワ、ローマで撮った写真があります。もちろんパリで、学生運動や、ファッション写真を始めいろいろな写真を撮っている。けれどどこにいようと、誰を被写体にしようとクラインの眼差しは不変です。
徴兵でクラインがヨーロッパにやってきた偶然をわれわれは喜ばねばならない。パリに来て、そしてフランス娘に恋をしなかったら、クラインは写真家にはならなかったように思います。パリにいたからこそ、クラインはアルジェリアに、モスクワにさらには東京まで行く。 ニューヨークを写真に撮る。会場で放映されていた白黒ヴィデオで、アルジェリアやモーリタニアの民族衣装の青年達が街なかをデモンストレーションするってのがあります。そこから突然68年のパリの街頭デモ映像に移る。あくまで自然に。。。パヴェ/敷石を掘り出し、バリケードを造る、車の燃えカスが横たわる。。。クラインはいつでも群集の中側にいる。
 今回の展示準備にクライン自身かなり関わったようです。赤・黒・黄色と、壁にカーブを使った展覧形式もクラインっぽくってよかった。人も多過ぎずゆったり見られました。
今回の展示準備にクライン自身かなり関わったようです。赤・黒・黄色と、壁にカーブを使った展覧形式もクラインっぽくってよかった。人も多過ぎずゆったり見られました。
せっかくパリにいるんだから、もっと“アート”しちゃおうと思うこの頃です。
投稿情報: 2006-01-24 カテゴリー: Art | 個別ページ | コメント (3) | トラックバック (1)
2006-01-23
2006-01-19
極東の対話欠如--ルモンド記事翻訳
極東でのナショナリズムの広がりと、中国・韓国・北朝鮮・日本、、+アメリカの絡む現状況と日本歴史のブラックホール、そして歴史否定主義について、(確かバンコク支局の)ドロンと東京支局長のポンス氏の記事訳出です。
極東での対話欠如
Dialogue manqué en Asie orientale, par Francis Deron et Pilippe Pons
ル・モンド記事(06.01.18日付)
外国排他ナショナリズムの広がりは、新しい潜在的冷戦の形をとっており、中国と日本の対立から、アメリカ合衆国と中国の対立へのシフトとも見てとれるだろう:北西アジアで立ち上がる緊張を描く危険なシナリオには事欠かない。内政への影響を計算した政治関係者の(各国間)不調和利用の後ろには、一方に中国と北朝鮮の関係悪化が、またもう一方には中国と日本の関係悪化があり、それらは新たな紛争の原因となりうるだろう。
いくつかの疑念要素が、世界のこの地域を不安に陥れる。ここでは意見の違いを議論し同意の基礎となすような対話の場が不足している。中国の経済発展という重みが日本から地域リーダーとしての立場を奪い、国内では軍事大国という属性への野望が活性化する。かつて親米反共の砦だった韓国ではアイデンティティ意識が強調され、北朝鮮との和解が促進、社会・政治変革が進んでいる。
これまでは、制度機構間の歩み寄りよりもプラグマティスムが、アジア共同体を押し進めた要因だった。大幅な人口増加にともなう地区の消費渇望は、地域内での交易の増大を生み、やがて必然的に経済と政治のより大きな統一性が求められる。しかしながら、12月中旬マレーシアのクアラルンプールで開かれた16カ国参加の東アジアサミットは、この地域の文化・政治・経済の多様性と相容れるような 『開かれた地域主義』 へ向かうべき決定的一歩を見せることはなかった。反対に、リーダーの不手際によって化膿してしまった過去の傷のためにプラグマティスムは躓き、その限界を見せた。リーダーたちは、現実の共同体組織に必要な最低の相互信頼(確立)に着手する。
特に中国と日本の敵対関係は、歴史的係争と地政学的ライバル意識、そしてエネルギー獲得競争に起因しており、地域の将来に大きく影響する。
呼び起こされた議論の重みを抱えたこの雰囲気の中では、ささいな偶発事も新しい論争の火種となる。中国情報局からの脅迫を招いたとされる2005年12月に明らかになった日本上海領事館エージェント自殺の件がこれにあたる。軍事予算増加率が二桁におよぶ中国からの『深刻な脅迫』についての日本国外務大臣Taro Asoの発言は、北京にショックを与えた。現在の中国と日本・韓国の関係において、極東には現実としての経済力がもたらすはずの親和原動力が、奇妙なかたちで欠如している。
小泉純一郎日本国首相の度重なる靖国神社訪問 -- ここには14人の戦争犯罪者、うち7人は極刑、を含む祖国のために死んだ魂が奉られている -- は、隣国から、過去の領土拡張主義の免罪化とみなされている。北京とソウルの延期依頼にも関わらず行われた前回10月の首相当神社訪問は、日本の尊大さの表明と受け取られた。東京によれば、小泉氏は日本の、過去を繰り返さないという使命を 『瞑想する』 ために靖国に赴くと言う。けれど、靖国に奉られた魂のなかには日本がサンフランシスコ講和条約によって受諾された国際法廷判決有罪者が含まれる。さらに、日本国首相は事を最小化する代わりに、新年演説の中で、中国および韓国が予定されていた会合を未期限延期した態度を激しく非難している。
日本における否定主義の復活
東京では、首相の靖国参拝の取り止めは中国の態度を変えることはないだろうと言われている。日本を孤立化させ、また地域内に確立させたい政略的パートナーシップ着手を目的に、中国は過去をツールとして利用している、というものだ。けれど(靖国)訪問を非難するのは中国ばかりではない。日本植民政策の犠牲者である韓国も同様な態度を取っている。そして、それ以外の同地域諸国(が小声で発する意見:原文では mezza voce )も、北京とソウルのとる観点からさほど遠いわけではない。それの反応として、これまで東京国際裁判判決に異議を唱えてきた日本右派は、直接近隣国に対する世論の感情的ナショナリズムに呼びかけようと試みる。
アメリカ合衆国はクアラルンプールに招かれてはおらず、会談は北京・東京間の強まる敵対心を目立たせるものだった。合衆国に密接に結び付けられた日本は、これまでの地域会談において、支配的強国システムの一部という立場をとっていた。今回の日本は単独で中国に対面した。
小泉政権は、ワシントンとの同盟に支えられ、自己の歴史観を中国に強いることが可能であり、また韓国もそれに倣うだろうと考えているようだ。中央アジア三国間の緊張に関して、アメリカ合衆国はこれまでのところ一歩引いた立場を取ってきたが、日本での否定主義といった現象が他諸国へ与える影響について、懸念を持ち始めている。
歴史書替えに関して、中国には教訓を与えうる資格などないのだが、1945年の敗戦以降、日本が平和主義を守り開発援助を通して地域経済興隆を助けながら、公的歴史において軍事時代の責任については明確にしない点をうまく利用することができるだろう。
小泉政権内で、この『ブラックホール』が自民党右派のカムバックと結びつき、安全保障上の利益を危険にさらすリスクがある。いずれにせよ、東京の態度は地域統合の障害となる。
『戦争犯罪者の前で頭を下げるこの人物』に関するいくつかのキラー(原文:assasines )台詞をもって、中国は現状況下では、これまでもその選択ではなかった地域マルティラテラル/多元主義カードを出す準備がないことを表わしている。中国は9月に予定される小泉後継者を待っている。その時までアジア2大国間関係が悪化し続けるリスクがある。
****
ところで全然関係ない話なんだけど、パリに舞い戻ってきたイスラエル娘と話してて、「なんか日本は合衆国の51番目の州だとか言ってる連中がいるんだよね、日本で。」って言ったら彼女「あ、それ間違ってる、だってアメリカの51番目の州はイスラエルなんだもん。」と反論されてしまいました。困ったもんだ。この現象を合衆国51番目の州ユニバーサリズムと名づけようかとか、、、いや別に意味はないですが。
追記:BSなんて高尚なもんはキャッチしてない同胞(猫屋を含む)宛のクリップ。NHK-BS1の番組「アメリカは日本をどう見ているか」を見たTORA氏による実況中継です。阿修羅から。
投稿情報: 2006-01-19 カテゴリー: Japon, trad/翻訳 | 個別ページ | コメント (8) | トラックバック (1)
2006-01-18
フェルメールと光と、何故かクリムト
 松岡セイゴー氏の千夜千冊最新版長編では、フェルメールとフランドル派と光がセイゴーまな板にのっています。このところセイゴー氏と猫屋の間にはまま(勝手な見方ですが)シンクロニシティが発生していて、(思いの内容は異なるけど)、不思議。たぶん、同様な想像世界マッピングをしてる人は多いんだろう。混沌/現実世界/冬→記憶/歴史→闇/中世/ボッシュ→光/フェルメールとか。(でもなんでスピノザまで行かないのだろう、、。)
松岡セイゴー氏の千夜千冊最新版長編では、フェルメールとフランドル派と光がセイゴーまな板にのっています。このところセイゴー氏と猫屋の間にはまま(勝手な見方ですが)シンクロニシティが発生していて、(思いの内容は異なるけど)、不思議。たぶん、同様な想像世界マッピングをしてる人は多いんだろう。混沌/現実世界/冬→記憶/歴史→闇/中世/ボッシュ→光/フェルメールとか。(でもなんでスピノザまで行かないのだろう、、。)
冒頭に挙げられている美学校は、ことに寄ったら放学されて困っていた当時の少年猫屋が行こうと一瞬思ったあの学校のような気がする。70年代前後には、ヘンな学校が案外あった。今は昔。しかしあそこに行ってたら今はどうなっていたことやら。
*
昨日はグラン・パレのウィーン展に行ってきた。冬の小雨の中一時間半近く並ぶ。どうも急に美術館に人が戻ってきたようだ。これもシンクロニシティだな。でもシンクロが講じて会場内は凄い混雑。上野の特別展みたい。
エゴン・シーレは18歳のころ入れあげた。18歳の自分に見せたらメチャ喜ぶであろうに、などとアホなこと考えながらほぼ素通り。この人の絵は見てるとこっちが痛くなってしまうのだ。風景画でさえ“身体”が苦痛で捻じ曲がっている。例外が妻を描いた Edithの肖像。いい絵です。シーレは1918年にスペイン風邪で死んでいる。妻はその3日前に死亡。、シーレ28歳。
ウィーンには今までにも行けなかったし、この後もいけるかどうか分からないのでとにかくクリムトの絵は本物を見ておくべき、と思ったのだ。それでクリムト(1862-1918)。
このところ頭の中の絵画部門はヴァン・アイクとかボッシュとかの占める割合が大きかったから突然の20世紀初頭に戸惑う。マティエールと人物の境界がだんだん曖昧になってくる。曖昧な霞の向こうから“まなざし”が見るものを見ている。物としての身体。金属。細部。単に人物画だけだったらクリムトもミュシャのようなアール・ヌーボーのデザイン画家で終わったのかもしれない。当時の、やってくる不幸への予感と結果するウィーンの退廃とが今回の展覧会の、クリムト・シーレ・ココシュカ・モザーたちの“狂気”の絵画を生み出したのだろう。
ウィーンの彼のアトリエには半裸の若いモデル達がいつもいて、クリムトは彼女達の動い たり眠ったりする姿をデッサンした、とどこかで読んだ。
たり眠ったりする姿をデッサンした、とどこかで読んだ。
ココシュカの絵を見るのは始めて。クリムトの風景画も。ココシュカの暴力。クリムトの、これもマティエールとしての風景。
わたしにはまだ、絵画を語る力がない。それで今日はこのままフェードアウトなり。
投稿情報: 2006-01-18 カテゴリー: Art | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
2006-01-14
猫屋のフリースタイル
まず地球のこと:
15年ほど前のことだろうか、某石油企業に働いていた友人から『中国国民が自転車を小型バイクに乗り換えただけで、地球大気汚染は後戻りの出来ない状態になる。』といった報告書の話を聞いた。そして15年が経った。
相変わらず地球温暖説は日本ではあまり人気がないようだが、今冬の日本大雪を見ても、繰り返す欧州・アフリカの洪水と日照り現象を見ても、またアフリカのエピデミー/伝染病の起こり方の変容(マラリアの流行季節変化等)を見ても、アルプスや南極の氷の解け具合を見ても、どうしたって地球大気の温度は上昇しており、何でもかんでも燃やすことで生計を立てている人間(燃やすことの出来る地区および層の)の営みが、公害いかんを問わず、地球大気と海水温度を上げる原因の一端をなすことは誰も否定は出来ないのだよ。
さて、中国は世界の工場としての使命を見事に果たしている。そして世界第四位の経済国になり(ランク付けに自信なし)、世界第二の汚染排出国(ランク付けに自信あり)となった。中国に資本投下しているのは米国・日本・ドイツ・フランス等の企業だが、中国製品を多く消費するのは(我等)貧乏人である。
そんな経過で中国では原油不足となり、アフリカ大陸に原油をはじめとする資源を求めるようになった。他の大国並みの“繁栄”を目指す中国とその国民に、省エネや代替エネルギー開発や汚染管理を要求してみても始まらない。中国産製品を必要としているのはわれわれだからだ。
原油供給をロシアばかりに頼るのは莫迦であろう。イラク攻撃に至った経過を見れば、誰もが中東原油には依存したくはない。旧英国領を別とすれば例外は日本であるが。
*
私の大まかな歴史観でいえば、19世紀は蒸気機関と神からの逃走/あるいは神の否定からの逃走、そして植民の時代であった。20世紀前半は戦争と亡命、20世紀後半は代理戦争と難民と“科学”の時代であった。資本主義勝利の時代でもある。フリーダム。
そして21世紀は? まずは失業の時代であろう。そして収入格差の増大。言い換えれば株式取引の活発化とM & A の繰り返しに伴って(本来は分配されるはずであった)富の集中化が加速する。同時にワーキング・プアーと呼ばれる人口層が大国都市部で生まれる。
“第3世界”では共産勢力の消滅から、過去の拮抗パワーバランスが崩れた。特にアフリカ大陸では貧困を土台に、権力の不在あるいは不能から起こる部族・氏族間抗争の上、資源を求める大国からの資本・軍力・経済援助が問題をさらに複雑化する傾向さえ見て取れる。
他方では、新しい形での植民戦争がイラク、チェチェン、イスラエル・パレスティナで繰り広げられている。だが、植民地政策が明らかにペイしないという事実を裏付けたのがかつての米国の経済台頭ではなかったのだろうか? また疲弊しきったイスラエルは、ガザ地区からのコロン/植民撤回という演出をせざるを得なくなった。( ガザからの8000人退去には6万人のイスラエル兵が動員され、世界中から8000人のジャーナリストが集まった。しかしパレスティナ人居住区を囲い込む壁建設は続いており、同時にウエストバンドでの植民も引き続き行われている。)
職を求めて荒れた国を逃れるのは難民ばかりではない。本来ならば国家建設をになうべき高等教育を受けた、あるいは海外留学した若年層も、より良い生活を求めて大国に生活の根を下ろす。逆に開発国からは企業や資本、一蓮托生起業人や観光人が旧第3世界を目指し、津波にあったり人質になったりヒューマニタリアンや傭兵やサポセン管理人になったりする。これがグローバリズム。
失業という病がナショナリズムという併発病をもたらすのはよく知られた現象である。だが、惜しむらくは、人間とは忘れることにかけては卓越した生物であることだ。あるいは“恥”という概念を持つ生物であり、自分に都合の悪い記憶は忘れるわけだ。
*
さて、仕事の関係上、日本政界のプリンス某氏とその御一行様パリ滞在に遭遇した友人の伝によると、プリンスと御夫人はさすがに気品と、気品の要求する無関心さとを持って行動していたが、同行するサポーターの皆さんはかなり、、であったと言う。母国の上流と下流との格差は単に短期的“金”の問題にすぎないと思える。文化資産なるものが現在でも存在するのかどうかは分からないが(少なくとも私は所有していない確信はあるにしろ)、日本で“文化資産”を最も保有する層とは、限定付きでの大学人と他でもないニートでオタクな下流人であるだろう。
*
フランスにおいては、失業問題は最もビュルネラビリティの高い移民と移民系若者、とくにバンリュウに住む人々をまず襲った。しかし犠牲者は彼らだけではない。郊外ゲットーの外にも、人口マス内に散らばる形で、アーティスト・低学歴者・教職員およびアシスタントの一部・シングル・マザー・外国人等が、また相次ぐ解雇に伴って放出された元管理職が一般職に就く関係でこんどはトコロテン式に一般職が臨時職に就き、そして臨時職が失業のブラック・ホールに落ちていく。Ainsi de suite....
たとえば仏大企業を支える株主には、もちろん米国年金ファンドを含む多国籍資本の占める割合が多い。つまり、仏国民があるいは政府がどう考えようとも、仏国経済再編成は進む。国営企業や国が何割かの株を所有する企業にしても、国際競争に生き残るにはインターナショナルなストラテジックマネージングのトレンドに遅れは取れない。(ところで、いつの間にか仏企業家の英語能力は向上した。) いずれにしても出血は止まらないだろう。
 だが、出血をそのまま放置する行為は政治ではない。諸問題への政府の具体的対応によって、つまり可能な法規制・社会政策・教育と研究・年金と健康問題・経済等々の政策面と、政(まつりごと)としての政府パフォーマンスの質によって、やってくるだろう未来は大いに違ってくることを忘れてはいけない。
だが、出血をそのまま放置する行為は政治ではない。諸問題への政府の具体的対応によって、つまり可能な法規制・社会政策・教育と研究・年金と健康問題・経済等々の政策面と、政(まつりごと)としての政府パフォーマンスの質によって、やってくるだろう未来は大いに違ってくることを忘れてはいけない。
資本が政治体内にみごとにパラサイトした時、世界資本主義ロジックはその姿を現す。
*
そして、blogsphere/ ブログスフェール左翼にあしたはあるのか?ないにしてもかまったことか。いずれにしても黙ってみている余裕などないのだ。まずは政治を逆パラサイトすべきである。
参考:ネブロ・アーカイヴより
パラノイア国家の保守革命と、棄てられた社会政策
京都議定書をめぐる、ね式グルグル思考
共同体のフォンダモンタルが消費という社会活動に集約されてしまっている、と考えてめまいに近い感覚に襲われる
追記:読み返したらひどく無残な文章だったので、翌日手を入れました。
投稿情報: 2006-01-14 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (17) | トラックバック (0)
何故か時間がないのでクリップのみ, フレンチイ・サポセン@japan
ル・モンドウェブ版おまけ的ブログから、Tokyo
在東京仏人が Can you deliver ? な製薬会社の通訳サポートを電話でする話です。
投稿情報: 2006-01-14 カテゴリー: Japon | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-01-12
《The Twenty Year's Crisis, 1919-1939 》 という本について
 現在猫屋亭積読書庫にあるこの本は、《歴史とはなにか》 のE.H. Carr の著作。欧州での開戦宣言が出される直前の1939年7月に出版されている。ソヴィエト専門だった元外交官にしてジャーナリスト・歴史家カーが、(私の想像では)かなり emergency な状態(当初は新聞掲載)で書いた文章であります。
現在猫屋亭積読書庫にあるこの本は、《歴史とはなにか》 のE.H. Carr の著作。欧州での開戦宣言が出される直前の1939年7月に出版されている。ソヴィエト専門だった元外交官にしてジャーナリスト・歴史家カーが、(私の想像では)かなり emergency な状態(当初は新聞掲載)で書いた文章であります。
《歴史とは、、》の方は清水幾太郎の名訳があり、私も現本と訳本を時々比べて感心する。クリントンの愛読書リストにも入ってますね。
しかし、《20年の危機》は難しい。2003年だったか、某巨大掲示板でこの本を読む企画がありまして、私は当時アク禁を食らっていたにもかかわらず、参加者の皆さんのご好意で他掲示板に書いた文章をコピペしてもらいながら、一時期参加させてもらった。残念ながらこの試みは、元文章の困難さもあり立ち消えになったけれど、大変楽しい経験でありました。
蛇足になりますが、もともと優れた英文読みでも、ましてや歴史本読みでもない猫屋は、原文をまず翻訳エンジンで仏語化して読み込んだ。文章内関係代名詞など、仏語に直した方が意味明確になる場合があるんですね。アイロニカルな表現も多いし、そのぐらい込み入った文章です。たしか、日本語訳も一度出版されたが、何時の間にか消え去っているようです。
実際に私が読んだのは、240ぺージ近い本書の70ぺージにも満たない。けれど、カーの絶望しつつも書き進む、リアリズムと理想主義が互いに位置関係を変えていくという図式を取りながら、西欧の思想・政治・経済が“歴史”を突き進んでいくありさまへの批判解読は、難解ながらもエキサイティングな経験でありました。
なぜ、この途中しか読んでない本書を今思い起こしてるのかと言うと、この著書に書かれた、アングロ・サクソン型資本主義がいかに市場拡張を必要とし、その限りにおいて米国ではフロンティアという植民行為に至ったか、なぜウィルソン理想論が現れそして失敗するのか、などが極めてシャープな形で示されておるからなのでありますね。こういったことは、他の多くの歴史家がすでに書いているのだろう。が、地政学国際関係論のはじめともみなされるこの《20年の危機》、リアルタイムで書かれた文章の抱える危機感に、いまさらながら驚くわけです。
ここで原文第四章が読めます。
たぶん、HDに残っているだろう訳文に読めそうな部分があったら、後日拾ってみたいです。
なお、私の持ってるのは2001年に印刷されてるペパーバックス版。表紙写真はヒトラーとその取り巻き(1935年3月17日)。仏語訳も出ていません。以下は目次、
The Twenty Year's Crisis, 1919-1939 by Edward Hallett Carr
An Introduction to The Study of International Relations
TO THE MAKERS OF THE COMING PEACE
Part 1
The Science of International Politics
1.The Beginnings of a Science
2.Utopia & Reality
Part 2
The International Crisis
3.The Utopia Background
4.The Harmony of Interests
5.The Realist Critique
6.The Limitations of Realisme
Part 3
Politics, Power & Morality
7.Nature of Politics
8.Power in International Politics : a)Militaly Power b)Economic Power c)Power over opinion
9.Morality in International Politics
Part 4
Law & Change
10.The foundation of Law
11.The Sanctity of Treaties
12.The Judicial Settrement of International Dispututes
13.Peaceful Change
Conclusion
14.The prospects of a New International Order
というわけで、約240ページでギリシャに始まる欧州思想を全部カバーしてます、凄い勢いで。読んだのは第四章の部分と五章の初めだけですが、レッセ・フェールがどうやってドミナントになったかとか、ダーウィンの研究がどうやって支配階級の役に立ったかとかの分析はスリリングです。この人の読みの続きで言えば、対テロ戦争は資本主義ロジックが必要とする市場拡大から演繹された帰結となるのかな。いや、これは蛇足。また上記原文URLのところではいろんな文献が見つかりますよ。(もちろん、読んでないけど。)
投稿情報: 2006-01-12 カテゴリー: Livre / 本 | 個別ページ | コメント (3) | トラックバック (0)







