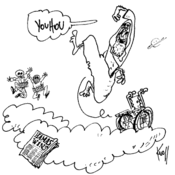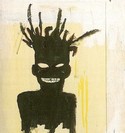ね式(世界の読み方)
Il faut cultiver son jardin
2006-01-28
画像日記、Hamas etc.
投稿情報: 2006-01-28 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
2006-01-26
改題: BHL もなー、など
 “Everything, my dear. I will tell you. Sometimes in your private life you have a mistress you love, love being with. You spend time to time in a grand hotel, with good room service, great champagne, and you separate—and when you are really in love with her, you inevitably think, Could I wake up with her, near her every morning ? And then you try it. This is exactly what I did in America. America was a great mistress. I had a great fuck with America. It was like a weekend in the Hotel du Cap.”
“Everything, my dear. I will tell you. Sometimes in your private life you have a mistress you love, love being with. You spend time to time in a grand hotel, with good room service, great champagne, and you separate—and when you are really in love with her, you inevitably think, Could I wake up with her, near her every morning ? And then you try it. This is exactly what I did in America. America was a great mistress. I had a great fuck with America. It was like a weekend in the Hotel du Cap.”
さて、今日は引用から初めてみました。で、クイズ。
“what did he like best about the U.S.?” という質問に上のような答えを出したファキン・アウトな人物は誰でしょうか?
回答は明日のブログで、、とすると続かないのですぐネタあかし:
これはNew York Magazine に掲載された BHL/ ベルナール・アンリ・レヴィの書評・インタヴュー最後部分です。
前後関係を解説しますと、われらがヌーベル・フィヒロゾフ生き残り軍団の一人BHL(57歳)は2004年、トックヴィルの跡をたどって合衆国を(運転手に運転させて)回ったわけだ。それで書かれた文章は月間紙The Atlantic にまず掲載され、今回“ American Vertigo ” として出版されたのですね。
なお、この本をめぐって、BHLとネオコン頭脳クリストルとのあいだに論争があったようである。ル・モンドの記事から、
France - Etats-Unis, le match Lévy-Kristol /フランスvsアメリカ合衆国、レヴィ-クリストル
NY駐在記者Corine Lesnes の記事タイトルを真に受けてはいけません。これはジョークだね。世界民主化=商業化、という大きな野望が結局世界ドツボ化に繋がった。このきわめて近所迷惑なアヴァンチュールの脳内製造元ネオコン論客を合衆国代表とみなすのも、同様にタレントさんにして女優さんの夫兼業のBHLをフランス代表と受け取るのも、短絡した昨今のメディア商法パロディでしょう。記事によると、ウォール・ストリート・ジャーナルはBHLを“anti-anti-américain”、New York Magazineは“rock star French philosophe”と形容。ふーん。ポスト・ジジェクをねらったアンチ・アメリカンマーケティングね。
残念ながら、該当BHL新刊を読む機会はないと確信ありなので、アメリカン・ヴァーティゴオへの言及はいたしません。そういやあ、テレビでは何回も見たけど、BHLの文章読んだことないわ。なお関係ないですが、他の欧州諸国に比べ仏国パスポート保持者の合衆国ビザ申請拒否率がかなり高いらしい。。。関連記事 500 000 Français privés d'Amérique
***
 こっちは冗談ではない、大変事であります。パレスチナ自治評議会選でハマスが勝利。
こっちは冗談ではない、大変事であります。パレスチナ自治評議会選でハマスが勝利。
関連ル・モンド記事、Le Hamas obtient la majorité absolue au Parlement palestinien
シャロンの軍人および政治家としての評価はさておき、怖いのは対するイスラエル権力空洞です。同時に、ネオコンの妄想した“力(+金)による民主主義確立”、東欧では今までのところ成功しているように見えますが、中東では逆にベクトルが動く。イラン・イラクもそうですが、世界地政無視界飛行の観がある。由々しい事態です。
****
さて、左上の写真はこないだネットで見つけたドアノー/Robert Doisneau の写真。いつものように本文とはまったく関係ありません。アプレ・ゲール@サンジェルマン、キャーヴ/地下のジャズクラブ風景と思われますが、夢見るように踊る彼女の表情と、それに魅入られる彼の視線がバンリュウの魔術師ドアノーによって永遠化されています。んー、写真って凄いですねえ。
*****
もひとつ追加: まえにも紹介したreso/レゾのアンチ・サルコサイトでこんなの見つけました。Kit de formationをクリックすると、
Que faire face à la police ?
Guide pratique du manifestant arrêté, rédigé par le syndicat de la Magistrature /ポリスを目の前にして、どうする?デモで捕まった時どうするかという法律専門家のアドヴァイス、とか
Voyage dans la gauche / 左翼の旅、をクリックすると左翼の歴史や有名人紹介ページなどにぶち当たります。まだ全部に眼を通してないけど、書き方は極めて正統派(?!)。フランスでの長いサの歴史がこうゆーのを可能にしてるんだろうね。A SUIVRE...
参考:それぞれのぺージURLをクリップできないのが残念。またフランス語読みでは(まだ)ないレクターは、これとか使って英語化するといいと思う。 また、この仏語ぺージではいろんな翻訳ツールが見つかります。
投稿情報: 2006-01-26 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (0)
2006-01-25
ウサマとマーケティング
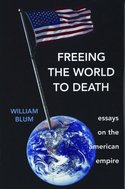 この頃、(不思議な現象だが)こちらではあんまり話題に登らない米国なんですが、これは面白い。ベン・ラデンが久々にメディアに登場、『アメリカ人、この本読むべし。』と、2000年に出版された “Freeing The World To Death アメリカ帝国に関するエッセイ” という本を(結果的に)プロモートしたわけ。おかげで米アマゾンで205763番目にランクされてたこの本、いっぺんにチャート26番目になっちゃった。
この頃、(不思議な現象だが)こちらではあんまり話題に登らない米国なんですが、これは面白い。ベン・ラデンが久々にメディアに登場、『アメリカ人、この本読むべし。』と、2000年に出版された “Freeing The World To Death アメリカ帝国に関するエッセイ” という本を(結果的に)プロモートしたわけ。おかげで米アマゾンで205763番目にランクされてたこの本、いっぺんにチャート26番目になっちゃった。
恐るべき影響力なんですが。ま、青年ベン・ラデンを対ソ戦でクリックし続けてあそこまで育てたのは米国CIAだったりしますから、論理的整合性がないといえない事もございませんね(恐怖の二重否定使ってみました)。恐るべきマーケティング自家免疫性抗原病なり。また、かのウォルフォ氏は世界銀行内部清掃でお忙しいようですし、結局宇宙空間はワープしてて、自分の投げたブーメラン石が(翌日訂正:ブーメランは直線空間でも戻ってくるがね、)自分のアタマ後部にぶち当たる可能性大なのでしょうか。コイズミさんもキヲツケよー。
関連ワシントン・ポスト記事。
投稿情報: 2006-01-25 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (4) | トラックバック (0)
2006-01-14
猫屋のフリースタイル
まず地球のこと:
15年ほど前のことだろうか、某石油企業に働いていた友人から『中国国民が自転車を小型バイクに乗り換えただけで、地球大気汚染は後戻りの出来ない状態になる。』といった報告書の話を聞いた。そして15年が経った。
相変わらず地球温暖説は日本ではあまり人気がないようだが、今冬の日本大雪を見ても、繰り返す欧州・アフリカの洪水と日照り現象を見ても、またアフリカのエピデミー/伝染病の起こり方の変容(マラリアの流行季節変化等)を見ても、アルプスや南極の氷の解け具合を見ても、どうしたって地球大気の温度は上昇しており、何でもかんでも燃やすことで生計を立てている人間(燃やすことの出来る地区および層の)の営みが、公害いかんを問わず、地球大気と海水温度を上げる原因の一端をなすことは誰も否定は出来ないのだよ。
さて、中国は世界の工場としての使命を見事に果たしている。そして世界第四位の経済国になり(ランク付けに自信なし)、世界第二の汚染排出国(ランク付けに自信あり)となった。中国に資本投下しているのは米国・日本・ドイツ・フランス等の企業だが、中国製品を多く消費するのは(我等)貧乏人である。
そんな経過で中国では原油不足となり、アフリカ大陸に原油をはじめとする資源を求めるようになった。他の大国並みの“繁栄”を目指す中国とその国民に、省エネや代替エネルギー開発や汚染管理を要求してみても始まらない。中国産製品を必要としているのはわれわれだからだ。
原油供給をロシアばかりに頼るのは莫迦であろう。イラク攻撃に至った経過を見れば、誰もが中東原油には依存したくはない。旧英国領を別とすれば例外は日本であるが。
*
私の大まかな歴史観でいえば、19世紀は蒸気機関と神からの逃走/あるいは神の否定からの逃走、そして植民の時代であった。20世紀前半は戦争と亡命、20世紀後半は代理戦争と難民と“科学”の時代であった。資本主義勝利の時代でもある。フリーダム。
そして21世紀は? まずは失業の時代であろう。そして収入格差の増大。言い換えれば株式取引の活発化とM & A の繰り返しに伴って(本来は分配されるはずであった)富の集中化が加速する。同時にワーキング・プアーと呼ばれる人口層が大国都市部で生まれる。
“第3世界”では共産勢力の消滅から、過去の拮抗パワーバランスが崩れた。特にアフリカ大陸では貧困を土台に、権力の不在あるいは不能から起こる部族・氏族間抗争の上、資源を求める大国からの資本・軍力・経済援助が問題をさらに複雑化する傾向さえ見て取れる。
他方では、新しい形での植民戦争がイラク、チェチェン、イスラエル・パレスティナで繰り広げられている。だが、植民地政策が明らかにペイしないという事実を裏付けたのがかつての米国の経済台頭ではなかったのだろうか? また疲弊しきったイスラエルは、ガザ地区からのコロン/植民撤回という演出をせざるを得なくなった。( ガザからの8000人退去には6万人のイスラエル兵が動員され、世界中から8000人のジャーナリストが集まった。しかしパレスティナ人居住区を囲い込む壁建設は続いており、同時にウエストバンドでの植民も引き続き行われている。)
職を求めて荒れた国を逃れるのは難民ばかりではない。本来ならば国家建設をになうべき高等教育を受けた、あるいは海外留学した若年層も、より良い生活を求めて大国に生活の根を下ろす。逆に開発国からは企業や資本、一蓮托生起業人や観光人が旧第3世界を目指し、津波にあったり人質になったりヒューマニタリアンや傭兵やサポセン管理人になったりする。これがグローバリズム。
失業という病がナショナリズムという併発病をもたらすのはよく知られた現象である。だが、惜しむらくは、人間とは忘れることにかけては卓越した生物であることだ。あるいは“恥”という概念を持つ生物であり、自分に都合の悪い記憶は忘れるわけだ。
*
さて、仕事の関係上、日本政界のプリンス某氏とその御一行様パリ滞在に遭遇した友人の伝によると、プリンスと御夫人はさすがに気品と、気品の要求する無関心さとを持って行動していたが、同行するサポーターの皆さんはかなり、、であったと言う。母国の上流と下流との格差は単に短期的“金”の問題にすぎないと思える。文化資産なるものが現在でも存在するのかどうかは分からないが(少なくとも私は所有していない確信はあるにしろ)、日本で“文化資産”を最も保有する層とは、限定付きでの大学人と他でもないニートでオタクな下流人であるだろう。
*
フランスにおいては、失業問題は最もビュルネラビリティの高い移民と移民系若者、とくにバンリュウに住む人々をまず襲った。しかし犠牲者は彼らだけではない。郊外ゲットーの外にも、人口マス内に散らばる形で、アーティスト・低学歴者・教職員およびアシスタントの一部・シングル・マザー・外国人等が、また相次ぐ解雇に伴って放出された元管理職が一般職に就く関係でこんどはトコロテン式に一般職が臨時職に就き、そして臨時職が失業のブラック・ホールに落ちていく。Ainsi de suite....
たとえば仏大企業を支える株主には、もちろん米国年金ファンドを含む多国籍資本の占める割合が多い。つまり、仏国民があるいは政府がどう考えようとも、仏国経済再編成は進む。国営企業や国が何割かの株を所有する企業にしても、国際競争に生き残るにはインターナショナルなストラテジックマネージングのトレンドに遅れは取れない。(ところで、いつの間にか仏企業家の英語能力は向上した。) いずれにしても出血は止まらないだろう。
 だが、出血をそのまま放置する行為は政治ではない。諸問題への政府の具体的対応によって、つまり可能な法規制・社会政策・教育と研究・年金と健康問題・経済等々の政策面と、政(まつりごと)としての政府パフォーマンスの質によって、やってくるだろう未来は大いに違ってくることを忘れてはいけない。
だが、出血をそのまま放置する行為は政治ではない。諸問題への政府の具体的対応によって、つまり可能な法規制・社会政策・教育と研究・年金と健康問題・経済等々の政策面と、政(まつりごと)としての政府パフォーマンスの質によって、やってくるだろう未来は大いに違ってくることを忘れてはいけない。
資本が政治体内にみごとにパラサイトした時、世界資本主義ロジックはその姿を現す。
*
そして、blogsphere/ ブログスフェール左翼にあしたはあるのか?ないにしてもかまったことか。いずれにしても黙ってみている余裕などないのだ。まずは政治を逆パラサイトすべきである。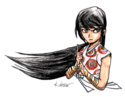
参考:ネブロ・アーカイヴより
パラノイア国家の保守革命と、棄てられた社会政策
京都議定書をめぐる、ね式グルグル思考
共同体のフォンダモンタルが消費という社会活動に集約されてしまっている、と考えてめまいに近い感覚に襲われる
追記:読み返したらひどく無残な文章だったので、翌日手を入れました。
投稿情報: 2006-01-14 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (17) | トラックバック (0)
2006-01-11
再度、クリップ・アップだけ
9日付けオピニオン・ページから、奴隷制度について
Traites négrières, esclavage : les faits historiques
6日付け、アナライズ・ページから、バンリュウとコミュノタリズム、失業、社会モデルなど
Banlieues, chômage et communautés, par Daniel Cohen
翌日追加、12日付けクロニック、たぶん翻訳不可能な
Fête, fastes, fatrasies et autres reliefs, par François Marmande
同じく12日付け、中国のアフリカ進出について
La Chine pousse ses pions en Afrique
投稿情報: 2006-01-11 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2006-01-09
も一度クリップス、クラップス
日本の毎日新聞から、縦並び社会シリーズ
仏共産党新聞 l'Humanité (1/04)からスラヴォイ・ジジェクのインタヴュー
La logique du capitalisme conduit à la limitation des libertés
資本主義ロジックは自由(複数)の制限に行き着く
一瞬訳そうかとも思ったんだが、少なくとも3日はかかりそうだし、レジュメ作りはまるでダメなので、ひとまずクリップのみ。なお内容は(ユマニテですので)欧州憲法関連、バンリュウ騒動、《ポスト・ポリティックス》、貧困、ネグリ=ハート批判、、、今回のは面白い。このぐらいの長さの文章がジジェクの本領発揮という気がします。長くなると三回転半芸が込み入ってついていけなくなる。
投稿情報: 2006-01-09 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (6) | トラックバック (1)
2005-12-22
Wikipedia
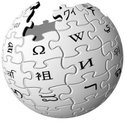 ルモンド関連記事
ルモンド関連記事
Wikipedia propose une version plus fiable de son encyclopédie gratuite
ファイナンシャルタイムズ関連記事Wikipedia plans site shape-up to counter "abuse" は残念ながら有料化しててアップできせん。のでこちらWikipedia to restrict access to encyclopaedia
ウィキぺディア創立者のJimmy Wales が19日のFT紙上で、ウィキを今まで通りの“フリー”ライヴ・ヴァージョンに、“間違い”の少ない点検済みヴァージョンを加えると発表したんですね。同時に新しい項目を書く、あるいは追加項目を書き入れる人物にまず登録を義務付ける、と言うもの。最近、アメリカ版のロバート・ケネディ・ページで、ケネディ兄弟暗殺に関連したとする人物の(ガセ)経歴が書き込まれた。フリーに書き込めるシステムで困る人も居るわけだ。
だが科学専門誌 Nature はこの12月に、科学分野に関してのウィキは百科事典ブリタニアと同じように“正しい”と指摘している。ウィキにアップされている項目は200万、200言語サイトがあり、そのうちの10言語全体で5万項目あるとか。
ネイチャーのウィキに対する批判は、項目の構造と、論争のネタ・セオリーの方に重点が置かれてしまう点だそうです。
んー、点検済みヴァージョンと言っても、だれがスーパーヴァイズするかがネックだし、ウィキを見てて面白いのは有機的リゾーム現象なんで、フリー・ソースがどこまで行くのか見極めたいとも思うんですが、同時にネット・ゾーンの“自由”がどこまで生き延びるか、、という問題でもあるな。どっかで“神の手”が現れそうな悪寒。
googleだって、結局ぜんぜん自由じゃないわけでね。やっぱり古本屋でポール・ヴィリリオの本を探そうと思う。
投稿情報: 2005-12-22 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2005-12-20
短絡日記
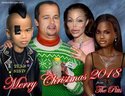 11月のはじめから5週間ほど、プレスを集中して読み込み訳出もして、結果狭い我が家は紙だらけになり、脳天は久しぶりにスッカーンとテンションが上がって、も、あかんかなとか思ったころに世間がいちおう落ち着いた。世間もル・モンドも私と同様疲れてしまったのだろう。
11月のはじめから5週間ほど、プレスを集中して読み込み訳出もして、結果狭い我が家は紙だらけになり、脳天は久しぶりにスッカーンとテンションが上がって、も、あかんかなとか思ったころに世間がいちおう落ち着いた。世間もル・モンドも私と同様疲れてしまったのだろう。
個人的には、また見えてきた事象もあるのである。世間さまが今何を感じているかはこの後また大事があってから出てくるのだろう。一歩前進二歩後退なのか、あるいは三歩前進、二歩後退であるのか。散歩全身、仁保交代。あしたはたまった新聞雑誌をリサイクル・ゴミ箱に捨てよう。
もう一回、『資本主義は、今、その発展の中ほどにあるに過ぎないのではないか。』 というスーザン・ソンタグがテレビで言っていた言葉を噛み締めている。
日本の財政赤字は1000兆円だそうだ。JMM最新号で金融専門家達が原因についていろいろ語っている。アメリカの財政赤字は4126億ドルらしい。フランスの数字はここにはないが累計負債が2ビリオンユーロを越える言う記事があった。、、、これらの数字が“本当に”指し示すものを知りたいわけでも、この三国の経済状態を比較したいわけでもない。だいたい私にはそんな能力はない。この各国の借金地獄がわれわれ生活人の日々の不幸の源泉だと言いいたいわけでも、もちろんない。
言いたいのは、世界でもっとも豊かなはずの国々がとてつもない財政赤字を背負い込んでおり、同時にこれらの国内部で貧困層が増え続けている、という事実だ。中国・ブラジルやインドの経済活動の急激な発展があるが、その新経済ゾーンでも貧困層がなくなる様子はないようだ。おまけに急激な開発は急激な自然破壊を伴う。60-70年にかけて日本の自然がどういう風に切り刻まれたかを、思い出す。
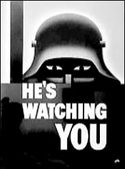 そして、成長率15パーセントというどう考えても非人間的数字をノルマにせざるを得ない株式会社経営が、“ヒューマン・リソース”を初めとするコスト削減でしか競争を続けていけない事実だ。結果としてのチキン・レース的終わりなき失業率増大と、高所得者と低所得者の収入格差増大が世界中で起こっている事実である。
そして、成長率15パーセントというどう考えても非人間的数字をノルマにせざるを得ない株式会社経営が、“ヒューマン・リソース”を初めとするコスト削減でしか競争を続けていけない事実だ。結果としてのチキン・レース的終わりなき失業率増大と、高所得者と低所得者の収入格差増大が世界中で起こっている事実である。
短期的に見れば、米国では対テロ戦という名の侵略戦争での出費、そして原油高という複合的経済理由が挙げられるのだろうし、日本ではバブル崩壊後の経済政策の不味さが挙げられると思う。経済先進国一般で言えば、人口の高年齢化と国家支出増大、伸びない経済成長率があるのだろう。
 だが、そういった“経済先進国”での経済的行き詰まりの個々の“原因”とは別のところで、もっと長いスパンで起こっている現象について考えている。端的にいえば、われらが生きる新資本主義時代の行く末、についてである。“自由”を掲げる“資本主義”が人間をどんどん不自由な状態に追い込んでいる。競争原理が、個人間のヒエラルキーを強化させ、自己よりも下にいる(と想定した)他者の排除に誰もが躍起になる。消費するがゆえに、我あり。そこでは、単により多く消費するものが勝者なのだろう。
だが、そういった“経済先進国”での経済的行き詰まりの個々の“原因”とは別のところで、もっと長いスパンで起こっている現象について考えている。端的にいえば、われらが生きる新資本主義時代の行く末、についてである。“自由”を掲げる“資本主義”が人間をどんどん不自由な状態に追い込んでいる。競争原理が、個人間のヒエラルキーを強化させ、自己よりも下にいる(と想定した)他者の排除に誰もが躍起になる。消費するがゆえに、我あり。そこでは、単により多く消費するものが勝者なのだろう。
*
久しぶりに訪れた松岡セイゴー氏のサイトから、、、
『西田幾太郎哲学論集』
『アンチ・オイディプス』 ドゥルーズ・ガタリ
『情報化爆弾』 ポール・ヴィリリオ
大病から帰還した松岡氏はこのところ大作相手に読みを続けている。建築家であり、パリ建築大学の長であるポール・ヴィリリオ/Paul Virilio に関する松岡氏の文章から引用してみよう。
脳がアナロジーを担当すべきところを機械がテクノロジーで代替してしまったのだ。一言でいえば今日のIT社会の問題のすべてが、この「アナロジーからテクノロジーへ」ということに集約される。
こんなことは世の中を見ていれば至極当然な推移だと思っていたのだが、意外にも誰も指摘してこなかった。もっとも世の中の推移を見抜くには少しは鍛練がいる。縮めていえば「人間の生物的な本来」と「文化の社会的な将来」の両方についてちょっとばかり思索を深めていなくてはいけない。もっと短く縮めていえば「脳と言葉」「経済と機械」の両方の問題を解くスコープが同レベルで重なって見えてなければならない。世の中の推移を見るには、大脳主義者ふうの唯脳論や言語主義者ふうの素朴意味論者やMBAふうの予測に走る経済主義理論では、まったく役に立たないのだ。「脳と言葉」「経済と機械」をいつも連動させて見る必要がある。‥ベネトンがやったことは誰が誰をメディア化するのかという広告テロ戦略だった。広告はメディアの裂け目を見いだすしかなくなったのだ。‥映像の検閲がゆるゆるになるにしたがって、映像作家たちの想像力がさらにゆるゆるに衰えている。それより速く観客の想像力は枯渇する。
‥CNNのせいで、いまや大衆はどこの国に対してもホームシックにかかれるようになった。その病気に罹らなかった連中は、たいてい自分に対してホームシックになっている。‥自動車の著しいハイテク化は、建物の一部を切り離してコンピュータにして、そのあとに4つの車輪をついでにつけたようなものだった。それでも事故がおこるのだから、あとは無視界コックピットが待つだけだ。‥ユビキタスな電子住宅こそ監獄である。閉じ込められれば閉じ込められるほど便利になるというのだから。‥OPA(株式公開買付制度)が残された経済的自由だと思えるのは、1秒後の瞬間情報を確信したいからである。きっとその情報が自分のところに来たものだと思いすぎたのだ。‥選挙はとっくにサブリミナル戦争になっている。政治がカジノになるのは投票者が博打が好きになっているせいだろう。・・・
**
読み通せないことはわかっているが、ヴィリリオの本をさがしてきて積読書架に加えようという気になる。you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one.....
投稿情報: 2005-12-20 カテゴリー: Economics/経済, Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
2005-10-06
三題話、l'entracte
 あいも変わらずペンギンです。見てて飽きない。映画見に行っちゃいそうな勢いですが、DVDがもう出ている。しかし南極風景は大画面の方が向いてるからして、友人の子供でも借りて一緒に見に行こうかなんて考えているわけで、、、ま、閑話休題。
あいも変わらずペンギンです。見てて飽きない。映画見に行っちゃいそうな勢いですが、DVDがもう出ている。しかし南極風景は大画面の方が向いてるからして、友人の子供でも借りて一緒に見に行こうかなんて考えているわけで、、、ま、閑話休題。
この本来地味系映画が受けちゃったのは、ペンギンの姿が人間に良く似てるってことが①、けなげなペンギンの“家族愛”が②、なんだと思います。②の派生として、ペンギンのお父さんぶりは見習いたい、といった受け取りも出来るわけです。
たしかに、ぼろぼろになりつつ河を上って産卵するメス鮭は二本足で歩かないし、だんなさん鮭とキスしたりしないから絵にならない。子供がイクラ・スジコでは、親子記念写真も取れないし。
ダークスーツ着こんだペンギン父さんの息子との会話なんて、まったく今時の親子関係では(TVや映画以外では)なかなか見られないよい風景であります。いや、大体この見方がよろしくない。大体、あれはお父さんじゃなくて、お母さんかもしれないでしょが。
それに、ペンギンが生きているのは“家族愛”ではなくて“種の継続”への意志みたいなもんでしょう。
セントラル・パークの動物園には、ロイとシロというペンギン・ホモカップルがいるんだそうです。さすがニューヨーク。ついでに書いとくと、ペンギンの一夫一婦制は続いて一年だそう。つまり子供が独立するまでですね。ははは。
要するに、父性のはなしにペンギンの写真を持ってきたのは、まあ翼があっても飛べない抑圧性(インポテンツのことかも)までは行かないにしろ、偶然ではなくて、“親と子”の関係性のためだったような気もします。“ね”の潜在意識ちゅうーか。
*
さて、関連2エントリ自分で読み返して、単語の誤用を見つけたんですね。“父性”がいつの間にか“父権”に入れ替わっている。これって案外微妙です。
吉本隆明は“父性”を背負った。これには“夫”であるという大前提があります。じゃないと“対幻想”が対幻想じゃなくなる。(共同幻想論は68年に刊行)
1945年生まれのニール・ヤングは10歳の時両親が離婚し、母親に育てられています。
フロイトのユダヤ・キリスト的父像には“父性”というよりも“父権”あるいは“父権性”が強いという印象を持ちます。どうしてか。
一神教の“父/神”は創造者であり、同時に子供を抑圧する存在ではないか、と思います。完璧な存在である“父/神”は自己が創造した子供/人間に、自分と同じように完璧な存在になることを期待するのですが、同時に“原罪”なるものも与える。原罪を抱えながら、父/神に近づこうとすること自体がパラドクスであって、子供としてはいったん“父/神”を殺さねばならなくなる、、、といったプロセスがあるように感じられます。
つけたしですが、“父権”が日本でも有効だった時代があります。明治から昭和の敗戦までですね。植民地政策の頃です。(明治以前については社会構造が異なると言うことにして勝手に略)
やがて、医学の発達があり家族あたりの子供の数が減少する。女性の教育程度が高まり、職業進出があり、フェミニズムがあり、同時に父親の育児参加が徐々に一般化する。平行的に離婚が増大し、核家族さえ崩壊し、再編成家族(子連れ離婚組み同士の再結婚)あるいは片親家族が増える。欧州では、まだ数は多くないにしろ、ホモセクシャル・カップルが子供を育てています。
もちろん先進国に関する事象ではありますが、この60年ですごいスピードで変化しているのは経済ばかりではない。
ジョン・レノンが息子ショーンの育児に専念していたころ(70年代後半)、そんな父はまだ例外的だったように思います。
“性”はどこかで“権力”と繋がる。政治になるんですね。力関係。ヒエラルキー。一神教的(中央集権)世界ではミクロの部分でもマクロの反復が見られる。家族内にヒエラルキーが出来上がる。ところが男と女の差が、労働面でも金銭面でも、少なくなってくるとこの構造が壊れる。屋台骨が壊れた家庭は分散しだして止まらない。(これは同時に政治自体の分散とクロス・オーバーしてるようでもある)
話はちゃらんぽらんと、どんどん無政府的に進むわけですが、むりやりまとめて見ると、ヨーロッパ的父権は20世紀後半になってからとんと人気がない。これはユダヤ・キリスト一神教の後退(そして、どこかでフロイト主義の後退)と無縁ではない。
古典的家族が崩壊して、社会の基本であった“家族”が核家族的“カップル”に集約され、そして一夫一妻制が崩れかけている(時間差ポリガミー)欧米では“親子”が“家族”のぎりぎりのベースをなしている態だ。
以前のブログで紹介した Broken Flower は息子探しの話だったし、チャーリーのチョコレート工場にも(フロイト風な歯医者)父親探しのエピソードが出てくる。今パリで封切りの映画のなかでも、アメリカ映画の Keane、ポルトガルの Alice の2本がいなくなってしまった娘を探す父親の話。恋愛よりSEXより(暴力ははっきり言って厭きたし)、子供への愛が勝っているように見える。
(ああ、そうか。かの国の、父権を失った大人になりきれない男共は、ペンギン映画を観てID(インテリジェント・デザイナ)の父を恋うのだよ。大変だな。)
簡単に言えば、集中権力の権化的父親を今頃目指しても、あるいは探してもしょうむない。“性”としての親よりも、“個”としての親を生きることしか選択肢はないんだろうな、と思う。---- もしも、ここまで読んでくださった方がいらしたら、とんでもない話につき合わせてまったく申し訳ない、、、--- 明確な結論もないまま今日の作文はヘタレにフェイド・アウトであります。
おまけ:先日ラジオをかけてたら、オノ・ヨーコの紹介で“ヨーコがいなかったらジョンは、ヘンドリックスやジャニス、ジム・モリソンのように早死にしていたかもしれない”とコメントしてた。そういう見方もできるな、確かに。
投稿情報: 2005-10-06 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (7)
2005-10-04
とりとめもなく、メモのメモ
 京都で仕込んだ風邪が気管支炎っぽくなってきて、あわててSOSmédecin(自己医院を持ってない往診専門一般医)呼んで抗生物質の処方をもらったのが10日前。かかりつけのホームドクターは休み明けと言うのもあるのだろうが予約が取れず、往診を頼むことにしたわけだ。午前中だったので、電話から往診までの待ち時間は30分。診察料は40ユーロ(通常一般医は20)。まあ、医者にかかるのは一年に一回あるかないかであるから、よしとする。
京都で仕込んだ風邪が気管支炎っぽくなってきて、あわててSOSmédecin(自己医院を持ってない往診専門一般医)呼んで抗生物質の処方をもらったのが10日前。かかりつけのホームドクターは休み明けと言うのもあるのだろうが予約が取れず、往診を頼むことにしたわけだ。午前中だったので、電話から往診までの待ち時間は30分。診察料は40ユーロ(通常一般医は20)。まあ、医者にかかるのは一年に一回あるかないかであるから、よしとする。
8日間は薬のせいだろう、眠くてだるくて咳は止まらん、でひどい状態だったわけだがやっと落ち着いてきた。今日は久しぶりに泳ぎに行った。それできわめて幸せである。腹が減ったので、ビーフシチューを作った。うまかった。
*
ネットでなんとなく拾ったペンギン画像だったが、これは仏映画《La Marche de l'empereur》 からのもの。この映画、米国では編集しなおし、音楽とコメントを変えている。米版タイトルは《March of peinguins》。リベのアメリカ発ブロガーはアメ版のほうが気に入ったと書いてるけど、私はどっちも見てないから判断できない。
トレイラー見比たら、モーガン・フリーマンがナレーションやってる米版はスター・ウォーズののりで、仏版はきわめてメランコリック。この差が面白い。なんと、米国ではこの映画をめぐって、ID(ほれ、あのインテリジェント・デザイナのことですよ)論争が盛り上がったのだそうだ。欧州ではとっくにクリアされてる問題だと思うわけですが、新大陸では150年たった今始まってるわけですね。日本でも過激反応する人間はいるんだろうなあ。付き合うことないのに。
**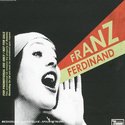 スコティッシュのロック・グループ Franz Ferdinandの新しいアルバムが出た。You Could Have It So Much Better という意味深なタイトルである。 むふ、Take Me Out よりよっぽど“イイ”のであるか。ちょっとラジオで聞いた曲はボウイ風であったな。前のアルバムは300万枚売れたのだそうだが(うち100万は米マーケット)、今回はあのネオ・スターリン的ルックは放棄したようである。ルモンドが一面記事にしていた。その記事部分。
スコティッシュのロック・グループ Franz Ferdinandの新しいアルバムが出た。You Could Have It So Much Better という意味深なタイトルである。 むふ、Take Me Out よりよっぽど“イイ”のであるか。ちょっとラジオで聞いた曲はボウイ風であったな。前のアルバムは300万枚売れたのだそうだが(うち100万は米マーケット)、今回はあのネオ・スターリン的ルックは放棄したようである。ルモンドが一面記事にしていた。その記事部分。
***
ダルフールの紛争がチャドに飛び火している。ルモンドに関連記事。フィガロの記事とチャドの大統領 Idriss Débyへのインタヴュー。
****
ジョルジュ・W・ブッシュは米最高裁判事(終身職9名)の一人に、Harriet Miers を指名。この60才になる弁護士さん、判事経験がまったくない。なんとテキサス時代のブッシュ州知事の個人弁護士だった人。当然ながらフレームがついた、と思ったら共和党右派が“彼女はpro-life度が足りない”と憤慨しているそうです。AFP関連記事。
投稿情報: 2005-10-04 カテゴリー: Monde / 世界 | 個別ページ | コメント (0)