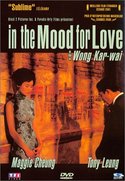2人で映画に行くと2人目はただ、というキャンペーンがあったので先週末は相棒と映画を2本見た。なんだかんだ言って、結局また米国映画である。50年代半ばに生まれた人間の“アメリカ刷り込みは”強いと言うべきかどうか、これは自分でも判断できないわけだが。
 Broken Flowers
Broken Flowers
英語では枯れた/しおれた花のことはwitheredと呼ぶのである気もするのでbrokenという形容詞は監督ジル・ジャルムッシュの“遊び”と考えた方がいいのかな。さて壊れてしまったのはいったいなんだったか、である。
今回のジャルムッシュの選択はBill Murray のでかい身体とあの顔にある。ロスト・イン・トランスレーションで、コッポラ嬢が(カメラで)なめまわした、あの中年男の無表情だ。おっさん顔である。メリー・クリスマス、Mrローレンスで北野武が見せた顔に遠くない。
仏人女優Julie Delpyが演じる連れ合いに愛想をつかれて出て行かれたマーレイが延々とTVを見てるときの顔は、なんと言うべきか。 無署名のピンクの手紙と、隣人のエチオピア系幸福男ウィンストンとのからみから、孤独な50男が20年前のガールフレンドたちに会いに行くロード・ムーヴィーなんですが、このガール・フレンドがシャロン・ストーンだったり、ジェシカ・ラングだったり。
20年前から映画を作ってきたジャルムッシュのある種の“映画”に対する愛情と、50歳代中ごろと思われるマーレイの身体からオーラのように滲み出す、なんと言ったらいいんだろう、人生に対する諦観にちかい悲しさが、表側を流れるエチオピア音楽の軽さの裏側に感じられます。
ウィンストンを演じるワシントン生まれのJeffrey Wrightはエチオピア訛りがうまく出てこないと、エチオピア大使館に電話して世話話したとか。スローな映画は猫屋の好み。 げらげら笑えるシーンも多いのに、最後の方で仮定形の“息子”を追いかけるマーレイの深い悲しみが分かると言うのは、これは猫屋も同様な年齢に達したと言うことなのか。(ちなみに、マーレイの現実の息子がこの最後のほうの一シーンに登場しているのだそう。) また、アメリカ家庭のいくつかのサンプルを提示する結果にもなってるね、この映画。
** Charlie & the Chocolate Factory
Charlie & the Chocolate Factory
1964年に書かれたRoald Dahlのベストセラーをティム・バートンが映画化したもの。この監督の映画はちとゴチックにすぎてあまり好きではないのだが、そこはそれジョニ・デップをゴチックに撮ってくれるならOK。見た結果はO.Kでした。
すべてtoo much、たとえばババロワ出身と思われるAugustus君とその母、US代表ゲーム・オタの破壊MIke君達は極限までカリカチュア化されている。デップの作りすぎメイクはロックスター、マリリン・メンソンをモデルにしたそうであるよ。
ちょっとチンタラ長かったけどOompas-Loompasクローンのミュージカル仕込みシーンは抱腹絶倒。 とっても貧乏だが何故かとっても性格の良いチャーリー君の母親を演じるのはHelena Bonham Carter、ティム・バートンの奥さんです。かわいい女性ですねえ。
MGMの水泳レヴュー映画や、2001年、マトリックス、スター・ウォーズとかからのパクリも多く、年寄りでも子供でなくても楽しめます。(追記:子供にはこの映画、毒が強すぎない?とか思ったけど今の子供は対毒抵抗力は強く、つまりさらに強いインパクトを欲しているという事実はあるわけですねえ。)
空間移動エレベーターは“ハウルの動く城”だろうな、と思う。工場のゴチック度もそうかな。 しかし、ティム・バートンが抱えている“空白を許容できない”創作精神状態はすごい。“ウィリ・ウォンカ”のテーマ・ソングはいまだに私の頭を去ってくれないのである。